環境と自然講演会
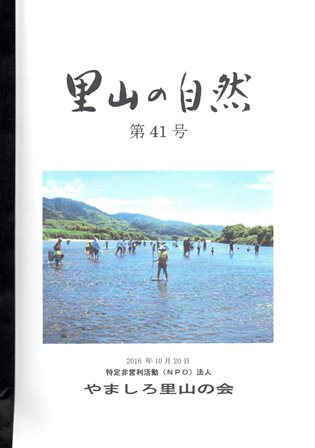 |
 |
どなたでも聴講できます。
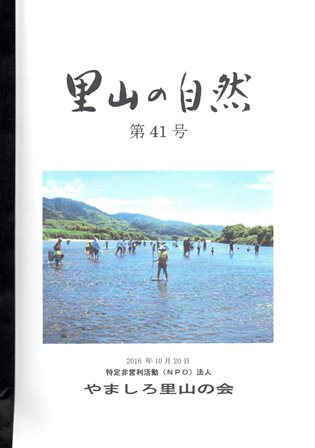 |
 |
| 回 | 講演日 | 会場 | 演 題 | 講 演 者 | 会誌号 | 記 事 |
| 里23 | 20190/03/03 | 中公 | 木津川における中聖牛の取り組み | 田住真史 京都大学4回生 |
46号 | 伝統的河川工法である「聖牛」による河床地形改変効果について |
| 環22 | 2018/09/01 | 中公 | 竹の花が咲いた | 小林慧人 京都大学大学院生 |
45号 | ハチクの花が60年ぶりに咲いています。その後の竹林の再生に関心をもちましょう。 |
| 環22 | 2018/09/01 | 中公 | 東南海地震その時どうする | 有本敏雄 元気象士 |
45号 | 東南海地震では震度6強から7が予測されます。日頃の防災意識を高めましょう。 |
| 里21 | 2017/09/02 | 中公 | 木津川の水運 | 鈴木康久 京都産業大学教授 |
44号 | 日本書紀にも登場する、木津川の水運の盛衰をわかりやすく話してもらった。 |
| 里21 | 2017/09/02 | 中公 | イタセンパラのこれから | 白波瀬卓哉 淀川河川事務所副所長 |
特別天然記念物イタセンパラの木津川での再生はできるだろうか | |
| 里21 | 2017/09/02 | 中公 | 里山活動に期待するもの | 西野麻知子 びわこ成蹊スポーツ大学教授 |
43号 | 中山間地での農林業従事者の減少は著しい。今こそ、里山活動が必要です |
| 環21 | 2017/03/04 | 山城支援センタ | カスミサンショウウオの生態 | 松井正文 京都大学名誉教授 |
42号 | 里山農園で見つかった絶滅危惧種カスミサンショウウオについて、その生態と生活しにつて、わかりやすく講演をいただきました |
| 里20 | 2016/09/11 | 山城支援センタ | 帰って来た天然海産アユ ~その保全と持続的利用を考える~ |
谷口順彦 淀川管内河川レンジャー |
41号 | 木津川のアユの多くは木津川で生まれて、大阪湾に下り、遡上してきた天然アユであることが実証された |
| 里20 | 2016/09/11 | 山城支援センタ | 琵琶湖内湖の魚類の現状と課題 | 北野大輔 滋賀県立大学大学院学生 木津川河川レンジャー |
41号 | 琵琶湖内湖に生息する魚類の現状を把握するために、彦根市の内湖(神上沼)の魚類調査を行った |
| 里20 | 2016/09/11 | 山城支援センタ | ハワイ島で40日間 ~植生と川が形成されていく島~ |
小林彗人 京都大学大学院生 |
41号 | 今年6月から8月上旬まで滞在していたハワイ島の植生や川の形成について |
| 里20 | 2016/09/11 | 山城支援センタ | 森里海連関 ~森と海をつなぐ川~ |
橋口俊也 京都大学大学院生 木津川河川レンジャー |
41号 | 森里海連関学の考え方により、大学院生の研究課題として水質の観点から考えてみた |
| 環20 | 2016/03/05 | 山城支援センタ | 地球温暖化における森林の役割 山城の里山のCO2吸収 |
小南裕志 森林総合研究所関西支所 |
40号 | 森林のCO2吸収などについて木津川市と交野市の山城試験地試験地で解明に取り組んでいる |
| 環20 | 2016/03/05 | 山城支援センタ | 木津川の河床環境の現状と 改善対策 |
竹門康弘 京都大学准教授 |
40号 | 木津川の河床環境の変遷と現状、及び竹蛇籠が木津川の環境に与える影響 |
| 里19 | 2015/09/12 | 中住 | 生物多様性と私たちの暮らし | 安生浩太 環境省近畿地方環境事務所 |
39号 | 環境省職員による生物多様性についての解説 |
| 環19 | 2015/03/07 | 山城支援センタ | 水害に備えて | 柗永正光 元淀川左岸水防組合収入役 |
38号 | 淀川における巨大な洪水災害の歴史と山城大水害の発生 |
| 里18 | 2014/9/06 | 北公 | 外来種問題を生物多様性から考える | 中井克樹 琵琶湖博物館学芸員 |
37号 | 琵琶湖の現状からみる |
| 里18 | 2014/09/06 | 北公 | 最近の活動から | 中川宗孝 ナチュラリスト |
37号 | 木津川読本「木津川ってどんな川」から |
| 里18 | 2014/09/06 | 北公 | 木津川の水質調査と地域 | 山田信人 河川レンジャー |
37号 | 木津川読本「木津川ってどんな川」から |
| 環18 | 2014/03/01 | 中公 | 日本百名山を完登する | 佐々木英夫 | 36号 | 山岳と絵画と歌の風景 |
| 環18 | 2014/03/01 | 中公 | 氷壁を登攀 | 佐々木健 奈良山岳会連盟理事 |
36号 | アルパインクライミング・アイスクライミングに取り組む |
| 里17 | 2013/08/31 | 城陽 | 里山をなぜ守るか? | 江南和幸 龍谷大学里山研究センター名誉教授 |
35号 | 日本列島の自然。人々の暮らしの歴史。里山のたどった道。文化の基礎を作った里山の恵み。近現代の里山。里山をとりもどせるか? |
| 環17 | 2013/03/02 | 中公 | 暮らしも地域・自然も壊す「原発震災とTPP」を考える | 渡辺信夫 渡辺地域経営研究所 |
34号 | 食、エネルギーの自給地域づくり」でふるさと再生と脱原発の道を |
| 里16 | 2012/09/08 | 城陽 | 秀吉と淀川 | 脇田修 大阪市歴史博物館長 |
33号 | 淀川の水運を活かして、京都を睨んだ秀吉と信長 |
| 環16 | 2012/03/03 | 中公 | 木津川の歴史と地域 | 中津川敬朗 山城郷土史研究会代表 |
32号 | 木津川の水運と地域の関係を歴史的に解説 |
| 里15 | 2011/08/28 |
社協 | 原発と放射能の正確な理解 のために |
市川章人 京都府立高等学校非常勤講師 |
31号 | 原発の仕組みと、その危険な本質、放射線の性質と被害の特徴など、具体的事実を正確に知って、正しく怖がり、正しく対処するために資料を提供する |
| 環15 | 2011/03/05 | 中体 | 京都府植物誌目録ノートと 山城の植物 |
光田重幸 同志社大学准教授 |
30号 | 山城地方の植物相について、詳しく解説 |
| 里13 | 2010/09/03 | 中公 | 宇治川の要・巨椋池 | 開沼淳一 国土問題研究会理事 |
29号 | 治水と環境の両面から巨椋池を考える |
| 環14 | 2010/03/ | 中体 | ふるさとの棚田と里山 | 北村貞太郎 京都大学名誉教授 京都府ふるさと保全委員会委員長 |
28号 | |
| 里12 | 2009/09/05 | 中公 | 「デ・レーケの大きな足跡」 | 島崎武雄 地域開発研究所 相談役会長 |
27号 | オランダの水利土木技術で |
| 里12 | 2009/09/05 | 中公 | 「木津川のこれからの整備」 | 小俣篤 淀川河川事務所長 |
27号 | 淀川水系の今後 |
| 環13 | 2009/03/14 | 中体 | 「地球温暖化と暮らし」 | 浅岡美恵 弁護士 |
26号 | 地球温暖化をどう見るか |
| 里11 | 2008/10/10 | 中公 | 穀物原油高騰・食糧危機とコペルニクス的転回の時代 | 渡辺信夫 顧問 |
25号 | 食糧・石油・金融・環境の複合危機と暮らしを考える |
| 環12 | 2008/03/02 | 社協 | 里山の生態学 | 櫻谷保之 近畿大学教授 |
24号 | 里山が果たしている役割について |
| 里10 | 2007/09/08 | 中公 | コウノトリの野生復帰と人との共生 | 大迫義人 コウノトリの郷公園主任研究員 |
23号 | コウノトリと共生する地域づくりをめざして |
| 環11 | 2007/03/03 | 社協 | 琵琶湖の環境問題 | 川那部浩哉 琵琶湖博物館長 |
22号 | 琵琶湖の環境問題4つについて |
| 里9 | 2006/09/02 | 中公 | 木津川の古代幻想 | 古川章 やましろ里山の会特別表 |
21号 | 万葉時代までさかのぼって木津川を考える |
| 里9 | 2006/09/02 | 中公 | シカの食草とオスジカの「縄張り宣言」 | 上島裕 やましろ里山の会顧問 |
21号 | 植物愛好家のシカの食草研究 |
| 里9 | 2006/09/02 | 中公 | 獣害から里山を守る | 野間直彦 滋賀県立大学講師 |
21号 | 獣との共生を考える |
| 環10 | 2006/03/04 | 中公 | 世界の水問題と暮らし | 神田浩史 NPO法人AMネット代表 |
20号 | 地球規模の水需給についての問題 |
| 環10 | 2006/03/04 | 中公 | 木津川の魚と私 | 福井波恵 木津川河川レンジャー |
20号 | 身近な木津川の魚との関わりについて |
| 里8 | 2005/09/03 | 中公 | 淀川の自然環境の保全と自然再生 | 村上興正 木津川中流域保全利用委員会委員長 |
19号 | 今後の人々の川との付き合い方について |
| 環9 | 2005/03/05 | 中公 | 山城の自然 | 佐伯快勝 浄瑠璃寺住職 |
昔の山城の自然と開発について | |
| 里7 | 2004/10/3 | 中公 | 自然と心 | 高垣忠一郎 立命館大学教授 |
生きることと自己肯定論 | |
| 環8 | 2004/03/06 | 中公 | 琵琶湖淀川流域の水環境の大切さ | 穂波宣員 琵琶湖・淀川水質保全機構常務理事 |
琵琶湖から淀川に至る水の水質保全について | |
| 里6 | 2003/09/06 | 中公 | 山城大水害から50年 「木津川が思わせてくれるもの」 |
宮本博司 淀川河川事務所長 |
木津川へ流出する土砂や砂防対策などについて | |
| 里6 | 2003/09/06 | 中公 | 「今昔物語 あれこれ」 人と川のかかわり | 太田 史 本会会員 |
長年河川行政に携わった体験談 | |
| 環7 | 2003/03/01 | 中公 | 市民の目で読む「沈黙の春」と日本の環境問題 | 高橋哲郎 前龍谷大学教授 |
レーチェルカーソン「沈黙の春」発刊40周年にあたって | |
| 環6 | 2002/03/02 | 商工 | 食の安全・農の再生と里山の価値 | 渡辺信夫 立命館大学講師 |
食の安全から里山を考える。ファーストフードの安全性 | |
| 環6 | 2002/03/02 | 商工 | カワセミに魅せられて | 小川正明 自然派写真家 |
長年、地元で観察してきたカワセミの写真を公開 | |
| 里5 | 2002/09/07 | コミュ | アジアの竹文化と日本の暮らし | 南出隆久 京都府立大学教授 |
循環型ライフスタイルにおける竹資源の利活用 | |
| 環5 | 2001/03/03 | コミュ | 古代の環境を読み解く | 井本伸廣 京都教育大学学長 |
化石と地層によって解き明かす地球の古環境 | |
| 里4 | 2001/09/01 | 中図 | ヨシ原の復元事業 | 小山弘道 鵜殿ヨシ原研究所長 |
30年にわたる淀川のアシ原復元報告 | |
| 里3 | 2000/09/02 | 中図 | 南山城大水害から学ぶ | 加藤哲夫 建設省木津川出張所長 |
昭和28年8月木津川大水害について | |
| 里3 | 2000/09/02 | 中図 | 南山城大水害から学ぶ | 川原林克美 京田辺市主婦 |
井手町在住の小学生の体験談 | |
| 環4 | 2000/03/04 | 中図 | 自立と共生 ゴミ問題と農業 | 槌田小劭 京都精華大学教授 |
「使い捨て時代を考える会」から考える環境問題 | |
| 里2 | 1999/09/04 | 中図 | 水生生物と自然 | 紀平肇 関西大学工学部講師 |
淀川ワンドの生物、ニホンバラタナゴの天然記念物指定への取り組み | |
| 環3 | 1999/03/04 | 中公 | 開会挨拶 | 岩佐英夫 弁護士、本会代表理事 |
最近の環境問題について思うこと | |
| 環3 | 1999/03/04 | 中公 | 桜と自然 | 佐野籐右衛門 第16代植藤 |
京で代々つづく櫻守からみた環境保護について | |
| 環2 | 1998/02/14 | コミュ | 開会挨拶 | 佐伯快勝 本会代表理事 |
浄瑠璃寺住職による「やましろ里山の会」 設立挨拶 | |
| 環2 | 1998/02/14 | コミュ | 防賀川の植物調査から見えるもの | 村田源 元京都大学講師 |
トキワススキとオオミズオオバコの確認 |